沼田城は、天文元年(1532)に当地に勢力を持っていた沼田氏12代の顕泰が、3年を掛けて築城し、当時は蔵内城と称していた。
沼田氏の出自は、平氏系の三浦氏の出であるという説や、中原氏系大友氏の流れという説など諸説があり、はっきりとはしていない。室町時代の関東の騒乱に際しては、関東管領山内上杉家に属して戦っていることが知られ、その後も山内上杉家に従っていた。
しかし、古河公方や関東管領といった旧権威が相争って勢力を衰えさせる中、伊豆から起こった北条氏が次第に勢力を拡げ、天文15年(1546)の河越夜戦で旧権威の衰退が決定的になると、同21年(1552)に山内上杉憲政が北条氏に圧迫されて平井城から沼田城へと落ち、さらにこの年か数年後、あるいは永禄元年(1558)に長尾景虎(上杉謙信)を頼って越後に落ち延びこととなる。
すると、沼田には北条氏の力が及び、顕泰も越後へ落ちたという。そして沼田城には、北条綱成の次男ともいわれる康元が入城し、沼田氏の名跡を継いだ。
その後、景虎が永禄3年(1560)に憲政を奉じて関東に出兵すると、上杉勢の攻撃によって沼田城は落城し、康元は城から落ち延びた。これによって顕泰が復帰し、以降は厩橋城と共に、後に謙信と名乗った景虎の関東経略の拠点として使われている。とは言え、上杉家臣河田長親が城番として城に在ったようで、以前のような沼田氏の独立的な支配が可能だったわけではないようだ。
この後、「加沢記」では、顕泰が子朝憲に家督を譲って天神山に隠居したものの、側室との間にできた末子景義を溺愛し、やがてこれに継がせるために朝憲を殺害したため、沼田家中は二つに割れてしまったとする。そして、永禄12年(1569)に天神山城が囲まれ、顕泰は蘆名氏を頼って会津へと落ち延び、沼田城は上杉氏が城代支配する城になったという。
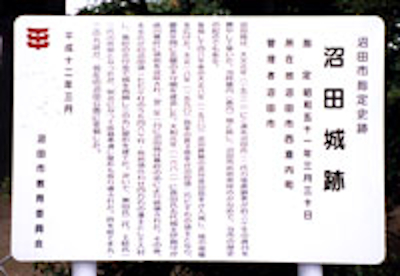
だが、「加沢記」は、後世に書かれたために部分的に信憑性が低く、何らかの争いはあったと思われるものの、実際にこの規模で争いが起こったのかどうかは不明である。ちなみに、「加沢記」では、上杉家臣の沼田城代の影が見えないが、「沼田市史」では、永禄9年(1566)まで長親が城番を務めた後は、松本景繁、河田重親、小中家成などの複数人で城番を務め、さらに小国重頼、新発田忠敦、上野家成も城番として名を連ねている。
天正6年(1578)になると、謙信没後の御館の乱で上杉家中が混乱し、一方の後継候補である景虎の実家として介入した北条氏が沼田城に再進出した。しかし、沼田城番衆の動きも、家中の動きを象徴するように一枚岩ではなく、翌年にはもう一方の後継候補である景勝側に立った上野家成が沼田城に籠城し、北条軍に攻略されている。
攻略後、城には猪俣邦憲、渡辺綱秀、藤田信吉が新たに城代として任命されたが、それも束の間、翌同8年(1580)に景勝と結んだ武田勝頼の命を受けた真田昌幸が、城代金子泰清、次いで同じく藤田信吉を降誘して無血開城させ、昌幸が城を支配した。さらに翌年には、北条氏と由良氏の援助を受けて旧本拠奪回に動いた景義を謀殺し、支配を確実にしている。
天正10年(1582)の武田氏滅亡後、真田昌幸は信長に従い、同年6月の本能寺の変後に織田家臣滝川一益が撤退すると、北条氏、次いで徳川氏の配下に入った。しかし、同年の天正壬午の乱という旧武田領の争奪戦を経て北条氏と家康が和議を結んだ際、上州は北条氏のものと決まったため、家康に沼田城の明け渡しを命じられたのである。
これに対し、替え地が不明確であったこともあり、昌幸は命令を拒んで上杉側へと奔り、信州上田に討伐に来た徳川軍を撃退して名声を高めた。これが第1次上田合戦である。

この後、天正17年(1589)に秀吉の裁定によって沼田城は北条方とされ、隣接する名胡桃城を真田氏のものとするように決まったが、沼田城に入った邦憲が同年に名胡桃城を攻撃したことから、私戦禁止に背いたとして小田原征伐の名目となり、翌年の小田原征伐で北条氏は滅亡した。
この時、沼田城は進軍ルートに入っていないことから、直接の戦闘は無かったと思われ、邦憲自身も箕輪城で防戦しており、他の上野の諸城の落城で孤立化した後、留守兵が降伏開城したのだろう。そして、戦後には昌幸の長男信之が城主となり、五層の天守を築いて近世城郭に改修している。
信之は、慶長5年(1600)の関ヶ原の合戦では、室の小松姫が徳川家臣の本多忠勝の娘であったことから、父と袂を分って東軍に属し、その功で父の領していた上田城を拝領して沼田を嫡子信吉に守らせたが、この系統は信利に至って天和元年(1681)に改易となり、城も翌年1月に破却された。後に沼田に入部した本多氏は、旧三ノ丸に館を造営したのみであったため、城が本格的に再興される事はなく、黒田氏、土岐氏と続いて沼田藩は維新を迎えている。
城は、利根川とその支流薄根川の合流点に近い台上にあり、利根川からはかなりの高度がある崖城であった。南は遠く片品川を防御線として、二方を断崖とする台地の西北端を本丸とし、東に二ノ丸、それらの南に三ノ丸が配され、本丸の北にも小さい郭が複数設けられている。低い位置にある水之手へは、これらの郭から降りることができたようだ。
真田氏改易に伴う破却によって、本丸と二ノ丸の石垣は埋もれているが、部分的に発掘された石垣を見ることができる。その他にも、本丸太鼓櫓や堀、土塁など、現代的な公園として整備されてしまっている割には見るべきものが比較的残っており、散策が愉しめる城だった。
最終訪問日:2001/9/30
崖下の川沿いの国道17号線から見上げると、いかに要害の地にあったかが解りますね。
国道から沼田城までは、恐ろしいほどの勾配を持った道を駆け上がって行くんですが、きちんと整備された2車線以上の市街地の道で、これほどの勾配がある道をあまり見たことがなく、それほど要害であったという証拠なんでしょう。